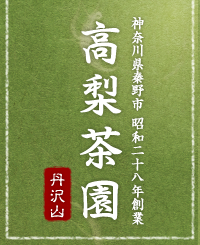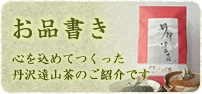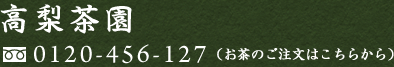煎茶のルーツ青柳製煎茶法と手もみ茶
江戸時代の1738年、京都府宇治の永谷宗円が、茶葉を蒸して揉んで乾かす「青柳製煎茶法」(現在の日本茶の元となった蒸し製法)を考案し、その評価が高まると共にその手もみ製茶技術が各地に広まった。
茶葉を蒸し、手で揉んで火力で乾かす青柳製煎茶法は、様々な人の努力と道具の発展、長い歴史によって改良工夫が加えられ、手もみ製茶法は今日の機械製茶の発明普及の原点となった。
機械製茶の普及と手もみ製茶の継承保存
明治末期に製茶機械の発明普及に伴い、茶生産は労力の軽減・大量生産の時代へと変わっていった。 一方、手もみ製茶は多大な労力・生産性の低さによりその重要性が薄れ、実用の範囲外に置かれていくことになり、優秀な技術保有者は極めて少数となっていった。
しかし、製茶機械の技術進歩が続いても、手もみ技術の応用と敏感な手の感覚の必要性が薄れる事はなかった。改めてその技術習得の研修や数多くの手もみ流派の熾烈な競争意識により、さらなる技術の追求がなされた。
そして、手もみ茶の形状は日常的・実用的な範囲を超え、芸術的域に達していき、「針の如く真直で丸く堅く撚れその剣先(先端)は障子紙を貫通する。色は鮮緑にして光沢は漆の如し」と例えられるような実に優美な茶を製造する技術に至った。
農産物の枠を超え、芸術的工作の域に達した手もみ茶は実際に作ってみると、かなりの体力と繊細な技術、根気を要する。
 しかし、根気よく揉むに従い、自分の茶が爽やかな香りを放ち、形状を整え、光沢を増していく姿に感動を覚える。あたかも芸術品を作るような心意気で、最後まで茶と向き合うのである。
しかし、根気よく揉むに従い、自分の茶が爽やかな香りを放ち、形状を整え、光沢を増していく姿に感動を覚える。あたかも芸術品を作るような心意気で、最後まで茶と向き合うのである。
 当園の四代目、高梨 晃は静岡県島田市にある、野菜茶業研究所にて2年間本格的に手もみ茶技術を習い、師匠、先輩、同期、後輩に恵まれた中で、真剣に手もみ茶技術習得のため練習に打ち込んだ。卒業後は、茨城県さしま茶の産地で、2年間研修を積み技術を高めた。
当園の四代目、高梨 晃は静岡県島田市にある、野菜茶業研究所にて2年間本格的に手もみ茶技術を習い、師匠、先輩、同期、後輩に恵まれた中で、真剣に手もみ茶技術習得のため練習に打ち込んだ。卒業後は、茨城県さしま茶の産地で、2年間研修を積み技術を高めた。
その後神奈川に戻り、県内の後継者を中心とした「神奈川県手もみ茶研究会」を平成22年に発足。神奈川県手もみ茶研究会として、全国手もみ茶品評会や、全国手もみ茶技術競技大会へ積極的に参加している。
また、手もみ茶技術の向上と、機械製茶への応用、茶園の日々の管理と改善点などをメンバーと共に議論し、自園の経営面でも理解を深め神奈川の茶業発展のため、技術・経営の両面で学びを深めている。
全国手もみ茶品評会
平成22年 第18回全国手もみ茶品評会 1等受賞
平成24年 第20回全国手もみ茶品評会 3等受賞
全国手もみ製茶技術競技大会
平成22年 第14回全国手もみ製茶技術競技大会 25位中第8位
平成23年 第15回全国手もみ製茶技術競技大会 32位中第7位